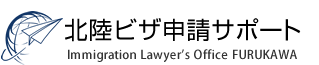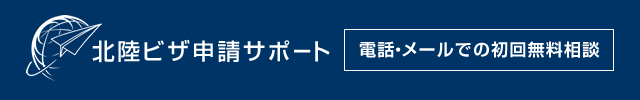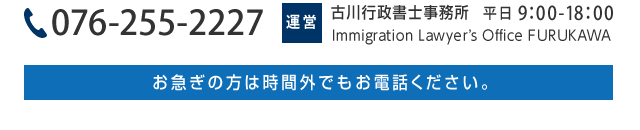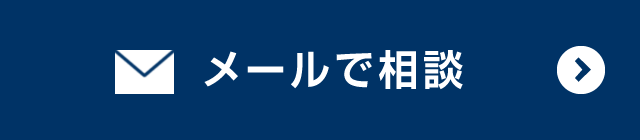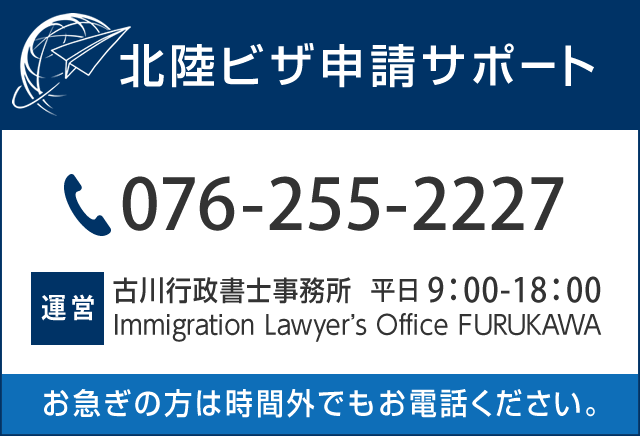外国人の入管業務専門の行政書士をしていますと、外国人業務に興味がある行政書士さんや社労士さんに「どうやって入管業務を学んでいけばいいですか?」と質問されることがあります。
ほかの業務と同じように、研修会・セミナーの参加、先輩の先生に尋ねるといった方法がありますが、私がまずお勧めしているのは本を読んで知識を増やすことです。
それは、本が一番コスパがいいからです。
セミナーだと数万円の参加費がかかることがありますし、先輩の先生と業務を一緒にやる場合、大抵は先輩の先生は指示をするだけなのに報酬は半分ということが多いでしょう。
また、入管業務は専門性が高いため経験があっても様々な疑問が生じることがあります。その疑問を解決してくれるのは、手元にある専門書であることが少なくありません。
そのため、まず専門書を揃えておき、それでも解決しなければ、入管(出入国在留管理局)に問い合わせたり、先輩の先生に聞いたりすることができます。
では、入管業務を扱うためにどんな専門書を揃えておくとよいでしょうか。
入管業務を専門にしている私が、実際に役立ったと実感した本をご紹介します。
※この記事のお勧めの本は、随時更新してゆきます。(最終更新:2023年10月)
入管業務をするなら持っていたい本
詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕 著者:弁護士 山脇 康嗣
【オススメ度★★★★★★】
入管業務するなら絶対に手元に置いておきたい“入管業務のバイブル”といってよい一冊です。この本は、入管法令、入管職員が参照する内部資料の審査要領、実際の制度の運用、過去の判例などを、国内で最も入管法に精通している弁護士がまとめたものです。内容は信頼でき、入管業務を遂行する際、頻繁に参照することになります。2022年9月に大幅に刷新されましたので、情報は最新です。
この本を購入するなら、必ず電子書籍ではなく、紙の書籍で買われることをお勧めします。電子書籍では、1100ページ以上あるこの本から該当の箇所を探すのは困難です。なお、この本は入門書ではないので、入管業務について何もわからない方は、後述する「外国人就労のための入管業務 入門編」などのライトな入門書をまず読まれることをお勧めします。
実務家のための 100の実践事例で分かる入管手続き 著者:行政書士 濱川 恭一、 行政書士 長谷部 啓介
【オススメ度★★★★★】
この本は、入管業務を行う上での経験不足を補ってくれる本です。入管業務では、許可要件を満たすことを申請人側が証明する必要があるため、法務省のホームページに載っていない資料を提出することが少なくありません。これが、入管業務の面白さでもあり、難しさでもあるのですが、「じゃあ一体どんな書類を提出すればいいか?」ということは、経験を重ねないとわかりません。しかし、この本を見ると、どのような資料を提出すると良いかが実例とともに紹介されており、とても役立ちます。
私はこの本を始めて読んだとき、正直感動しました。入管業務の専門家としてのノウハウや知りたいことが満載です!専門家に依頼するような案件は高難易度のものが多いですから、この本の情報はとても役立ちます。
外国人の入国・在留資格案内 著者:出入国管理関係法令研究会
【オススメ度★★★★★】
この本は、これまで一目で在留資格の要件や提出資料を確認できると好評だった「ひと目でわかる外国人の入国・在留案内」に替わるものとして、2023年10月に出版されました。この本は、外国人の在留資格の①概要、②要件(資格該当性、上陸許可基準)、③立証資料、④注意事項がわかりやすくかつ端的にまとめられています。以前のものと比べて、最新の情報が載っているだけでなく、より分かりやすくなったと感じています。在留資格の相談を受けたとき、依頼者がどの在留資格に該当するのか、どんな書類を確認する必要があるのかを判断するのは非常に重要です。在留資格の申請なら何でもしますよ、という方ならぜひ手元に置かれることをお勧めします。
知識ゼロからの外国人雇用 著者:竹内 幸一
【オススメ度★★★★☆】
この本は、外国人雇用に関する知識が全くない人に向けて書かれています。イラストもたくさん使われており、とても分かりやすいです。そのため、初めて外国人を雇用する企業様に説明するときや、就労ビザについて理解し、考えを整理するのに役立ちます。私のような行政書士は在留申請の許可がゴールと思ってしまいがちです。しかし、企業とってより重要なのは、雇用した外国人をいかに定着させるかです。この本のPART.4では「外国人の実力を引き出し、会社に定着させる」ための具体的な方法が取り上げられており、外国人を雇用している企業であればぜひ持っていてほしい一冊です。
注解・判例 出入国管理実務六法 令和5年版 著者:出入国管理関係法令研究会
【オススメ度★★★★☆】
その名の通り、入管業務に関係する法令がまとめられている入管業務における六法全書です。単に法令が載っているだけでなく、その法令の解説や判例も記載されています。そのため、説得力のある理由書を作成する際に、とても役立ちます。また、各申請・許可書・通知書の様式も掲載されているのも良い点です。入管の職員の方もこの本を活用しておられるようですよ。本格的に入管業務をされる方は、この六法を持っていると心強いのではないでしょうか。
外国人事件ビギナーズ ver.2 著者:外国人ローヤリングネットワーク
【オススメ度★★★★☆】
この本は、外国人関連の業務をこれから行なう弁護士さん向けに書かれています。そのため、この本を読むと、外国人関連業務のベースになる幅広い知識を得ることができます。外国人関連の業務を扱っている分厚い専門書をコンパクトにまとめた感じといったら伝わるでしょうか。ただし、この本のタイトルには「Beginners(ビギナーズ)」と書かれていますが、具体例が少ないため、これまで外国人関連業務の経験がない方は難しく感じると思います。
また、この書籍は、弁護士向けのため、主に行政書士が扱うことが多い入管業務についてはそれほど詳しく書かれていません。他方、弁護士が扱うことが多い外国人の刑事事件、訴訟事件、強制退去事件、難民事件などについては多くのページが割かれています。したがって、この本は、外国人関連業務を行なうすべての弁護士の方、在留特別許可の手続きを行なう行政書士の方、また、幾らか実務を経験した専門家の方が考えを整理するのにおすすめです。
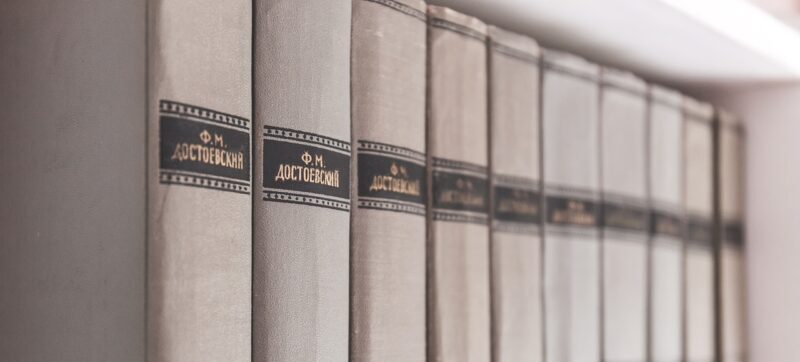
加除式書籍はどうなのか? 法律関係の出版社では、加除式書籍が販売されており、法律家の方ならまず加除式書籍を購入するという方も多いです。 そして、金額もそれほど高くない。 さらに、法改正などが生じ、内容が変更・修正された場合、該当ページ部分だけを差し替える「追録」が発行されます。 そのようにして、いつでも最新の内容を維持できます。 最高!? ただ、「追録」は有料で、けっこう高いです。 加除式書籍において、出版社が追録で稼ごうとしていることは明らかです。 その割に、加除式書籍を参照する頻度はそれほど多くない。 費用対効果が悪いので、外国人業務に専門特化することを決めてから、加除式書籍を購入されるほうがよいかもしれません。 なお、入管業務を専門にしている私が揃えている加除式書籍は以下の通りです。
それぞれの考え方があると思いますが、ご参考までに。 |
特定技能ビザを扱うなら持っていたい本
特定技能制度の実務―入管・労働法令、基本方針、分野別運用方針・要領、上乗せ告示、特定技能運用要領、審査要領― 著者:弁護士 山脇 康嗣
【オススメ度★★★★★★】
この本は、特定技能ビザの申請をするなら必ず持っておきたい一冊です。特定技能制度はとても複雑で関係法令も多いのですが、この本はそのほぼすべてを網羅しているという点で、極めて重要かつ貴重な専門書といえます。特に、特定技能ビザの審査で詳しくチェックされる労働関係法令にも多くのページを割いており、労働法の専門家ではない行政書士の知識不足を補ってくれます。まさに、特定技能ビザ申請におけるバイブルです。
技能実習ビザを扱うなら持っていたい本
技能実習法の実務 著者:弁護士 山脇 康嗣
【オススメ度★★★★★】
現時点(2021年2月)において、外国人技能実習制度や技能実習法などの関係法令や運用について的確にまとめられており、専門家が活用できるレベルにあるのは、この本だけです。そのため、外国人技能実習生を受け入れている企業や外国人技能実習の監理事業をしている事業協同組合からの相談を受ける方であれば、必ずこの本を持っておかれることをお勧めいたします。特に、技能実習法で義務付けられている外部監査人や外部役員に就任し、定期的に監査を行なう方にとっては必携の一冊です。
中小企業組合必携 総務・会計・税務の実務 2023-2024 著者:全国中小企業団体中央会
【オススメ度★★★★☆】
外国人技能実習の監理事業をしている事業協同組合から相談を受けていますと、組合運営や定款変更に関する相談を受けることがあります。その際に、組合運営に必要な情報がまとめられている本書は役立ちます。また、事業協同組合の職員の方はこの本に精通していなければ、的確に業務を遂行できないのではと感じます。
まとめ

中長期的な視点で考えるなら、今後、外国人が大幅に増加し、会社で外国人が働いているのが当たり前となる時代が到来します。その反面、外国人関連の法律や手続きは非常に複雑になっています。
そのため、入管業務はとても将来性があり、今から入管業務を取り扱い、手続きに精通しておくことは、専門家自身・士業事務所双方にとってとても有益なことです。
この記事が、外国人関連のお仕事をしておられる方やこれから入管業務を行っていこうと思っておられる士業の先生方に少しでもお役に立つなら幸いです。